電子帳簿保存法の改正に伴い、2024年1月から原則として事業者は電子取引のデータ保存が義務付けられています。
そのため、すでに法律に対応できるように進めている事業者がほとんどではないでしょうか。
しかし、まだ対応していない、もしくは不十分なケースもあり、場合によっては法律違反になる場合もあります。
法律違反となれば、罰則も気になるところでしょう。
そこで、本記事では電子帳簿保存法の罰則規定や該当するケース、対策まで解説します。
法律を違反しないためにも、ぜひ最後まで読み進めて、理解を深めていきましょう。
電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データとして保存するための法律です。
また、電子帳簿保存法は、主に3つの区分で構成されています。
1つ目は電子帳簿等保存、2つ目はスキャナ保存、3つ目は電子取引データ保存です。
これらの区分ごとに、データ保存の要件が定められています。
電子帳簿保存法に則って処理をすれば、類の保管スペースの削減や業務効率化、データ検索の簡易化などにもつながるでしょう。
ただし、法律で定められた要件を満たす必要があるため、注意が必要です。
電子帳簿保存法の罰則規定
電子帳簿保存法には、違反した場合の厳しい罰則が設けられています。
ここでは、主な罰則規定について解説します。
青色申告の承認取り消し
電子帳簿保存法に違反すると、青色申告の承認が取り消される場合があります。
その結果、青色申告特別控除が受けられなくなるため、個人事業主は大きな打撃を受けます。
法人の場合は、欠損金の繰越ができなくなり、税負担が増加する可能性があります。
さらに、青色申告の承認取り消しは、事業者の信用を損なうこともあるでしょう。
最終的には取引先や金融機関からの信頼を失い、事業継続に支障をきたす恐れもあります。
追徴課税や重加算税の課税
税務調査で法律違反が発覚した場合、追徴課税や重加算税が課される可能性があります。
場合によっては、所得や売上に対して10%の重加算税が追加されることもあるでしょう。
これは本来納めるべき税金に加えて、さらに10%の税金を支払うことになります。
また、帳簿の信頼性が失われると、税務調査の際に税額を推定によって決定する推計課税が行われる可能性も出てきます。
推計課税では、実際の収入よりも多く見積もられる傾向があり、本来よりも高額な税金を納めることになりかねません。
会社法による過料
電子帳簿保存法違反は、会社法第976条にも抵触する可能性があります。
会社法第976条では、帳簿や書類などの記録、保存に関する規定であり、電子帳簿保存法に違反すると同時にこの法律にも反する場合があるわけです。
会社法第976条の違反となった場合、最大100万円以下の過料が科されることも考えられます。
なお、過料は行政罰の一種であり、刑事罰とは異なりますが企業にとっては大きな負担です。
また、過料を科されることで、企業の社会的評価に悪影響を及ぼす可能性があります。
参考:e-GOV法令検索「会社法」
電子帳簿保存法の違反に該当するケース
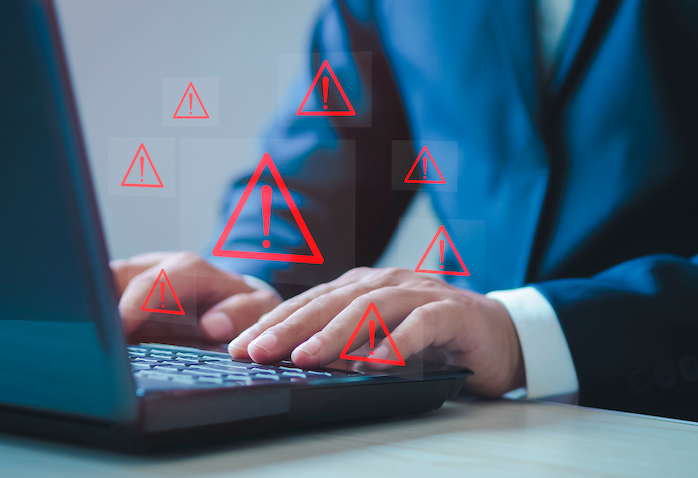
電子帳簿保存法の違反に該当するケースとして、5つの事象を紹介します。
違反となる理由を確認し、適切な対応に役立てましょう。
1.データ保存の要件を満たしていない場合
電子データの保存には、特定の要件を満たす必要があります。
たとえば、スキャナ保存を行う際に対象外の書類をスキャンしたり、解像度の設定を誤ったりすると違反となります。
これはデータの真実性や可視性が確保できず、税務調査などの際に正確な情報を提供できないためです。
2.検索要件を満たしていない場合
保存したデータは、いつでも簡単に検索できる状態にしておく必要があります。
この「可視性」の要件を満たさないと、法律違反となる可能性があります。
税務調査の際に迅速かつ正確な情報提供ができないことが、違反の理由と考えられます。
3.真実性の要件を満たしていない場合
電子データは、改ざんされていない原本の状態で保存しなければなりません。
これは「真実性」という要件であり、満たさないと違反となります。
理由はデータの信頼性が損なわれ、正確な税務申告や会計処理が困難になるためです。
4.保存期間を満たしていない場合
法定の保存期間内にデータを紛失したり破棄したりする場合も違反となります。
たとえば、請求書や見積書は法人で7年、個人事業主で5年の保存が必要です。
これらの書類は税務申告の根拠となるため、適切な期間保存されていないと、正確な税務処理ができなくなります。
5.電子取引データを紙で保存している場合
2024年1月からは、電子取引で受け取った書類は電子データのまま保存が必要です。
これらを紙に印刷して保存すると、法律違反となります。
電子データの原本性が失われ、データの改ざんリスクが高まるため、違反とみなされるでしょう。
電子帳簿保存法違反を防ぐための対策
電子帳簿保存法の違反を防ぐには、複数の対策を組み合わせて実施する必要があります。
そこで、効果的な5つの対策を解説します。
これらの対策を適切に実施することで、法令遵守と業務効率化の両立が可能になるでしょう。
適切なシステムの導入
電子帳簿保存法に準拠したシステムの導入は大事な対策の一つです。
そのため、クラウド会計ソフトなど、法令要件を満たすシステムを選びましょう。
そのようなシステムは、データの真実性や可視性を確保し、検索機能も充実しています。
導入の際はベンダーに法令対応の詳細を確認することをおすすめします。
また、自社の業務フローに合ったカスタマイズが可能かどうかも選定時のポイントです。
公益法人におすすめできるのは「WEBバランスマン」という会計ソフトです。会計が非常に便利になり、電子帳簿保存法にも対応することができます。
社内規程の整備
電子データの保存や管理に関する明確な社内規程を作成しましょう。
規程には、データの保存方法、保存期間、アクセス権限などを明記してください。
また、電子取引データの取り扱いについても具体的に定めておく必要があります。
そして、作成した規程は、全従業員に周知徹底することが大切です。
定期的な見直しも忘れずに行い、法改正にも対応できるようにしましょう。
定期的な内部監査
電子データの保存状況を定期的にチェックする内部監査体制の整備も必要です。
監査では、データの保存状態、検索機能の動作、アクセス記録などを確認します。
問題点が見つかった場合は、速やかに改善策を講じてください。
また、内部監査の結果は、経営層にも報告し、全社的な取り組みとして位置づけましょう。
そのため、年に1回以上の実施が望ましいです。
従業員教育の実施
電子帳簿保存法の重要性や具体的な対応方法について、従業員研修を行いましょう。
研修では法律の概要、違反のリスク、具体的な操作方法などを説明します。
特に日常的にデータを扱う部門の従業員への教育は大切です。
そのための施策としては、e-ラーニングの活用や定期的な勉強会の開催などが効果的でしょう。
新入社員研修にも組み込み、全社的な理解を深めることをおすすめします。
専門家への相談
税理士や公認会計士など、専門家のアドバイスを受けることも重要です。
専門家は最新の法改正情報や実務上の注意点を熟知しており、自社の状況に合わせた具体的なアドバイスを得られるでしょう。
定期的な相談を行うことで、継続的な法令遵守が可能になります。
また、税務調査への対応方法についても、事前に相談しておくとよいでしょう。
電子帳簿保存法の罰則規定のまとめ
2022年に電子帳簿保存法が改善されたことで、以前よりも保存要件が緩和され、帳簿や書類の電子化もしやすくなっています。
しかし、保存要件が緩和されたとはいっても、さまざまな規定があり、それを守らなければ法律違反に該当する場合もあります。
そのため、適切な対応ができるように、システムの導入や社内規定の整備などが求められます。
自社の体制や規定を再度見直して、電子帳簿保存法に違反しないように取り組みましょう。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




