企業や個人事業主が会計ソフトを導入した際に、購入費用をどの勘定科目で仕訳すべきか悩んでいませんか。「そもそも会計ソフトは経費になるのか」「会計ソフトの種類によって勘定科目は異なるのか」などの疑問を持っている方もいるでしょう。本記事では、会計ソフト購入時の勘定科目の選定や仕訳方法、処理方法について解説します。会計ソフトの勘定科目に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
会計ソフトは経費になる?

結論からいうと、会計ソフトの費用は全額経費として計上できます。会計ソフトとは、会計業務を効率的に行うツールです。事業に関する複雑な計算を自動的に行ってくれるため、事業に必要な支出と判断されます。
会計ソフトの購入金額が10万円を超える場合は、無形固定資産として減価償却できます。無形固定資産とは、固定資産の取得にかかった費用を耐用年数に応じて配分して計上する会計方法です。会計ソフトは自社利用目的となり、一般的に5年で減価償却を行います。
経費の勘定科目とは
勘定科目とは、会社の取引によって発生した現金の取引をわかりやすく分類するためのものを指します。会社の財務状況を明確にし、適切な会計処理を行うために必要不可欠です。
勘定科目は、「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つのグループに分類されます。グループ別の勘定科目一覧は次のとおりです。
勘定科目の一覧
・資産:流動資産(現金、当座預金、受取手形、売掛金、商品)、固定資産(建物、土地、機械装置、ソフトウェア、機械装置、車両運搬具、関連会社株式)、繰延資産(開発費)
・負債:流動負債(支払手形、買掛金、未払消費税、未払法人税等、未払費用)、固定負債(長期借入金、社債、退職給付引当金)
・純資産:株主資本(資本金、資本準備金、その他資本剰余金、繰越利益剰余金)、その他有価証券評価差額金、新株予約権
・収益:売上高、営業外収益(受取利息、雑収入)、特別利益(固定資産売却益)
・費用:売上原価(仕入)、販売費及び一般管理費(給料、家賃、広告宣伝費、交際費、消耗品費、通信費)、営業外費用(支払利息)、特別損失(固定資産除却損)
勘定科目にはさまざまな種類がありますが、代表的なものは会計ソフトで取り扱い可能です。勘定科目を増やす前に、使用している会計ソフトに当てはまるものがないか確認してください。一度設定した勘定科目は継続して使用することが重要です。
クラウド型会計ソフトの勘定科目
会計ソフトには、「クラウド型」と「インストール型」の2種類があります。クラウド型は、毎月または年単位で利用料を支払う形式のソフトウェアです。ここでは、クラウド型の会計ソフトの勘定科目について解説します。
「通信費」または「支払手数料」として計上
クラウド型会計ソフトの購入費用は、「通信費」または「支払手数料」として計上します。通信費とは、電話やインターネット回線の使用料などに対して使用する勘定科目です。クラウド型の会計ソフトは、インターネットを介してサービスを利用するため通信費に該当します。クラウド型会計ソフトには、主に月額制と年額制の種類があります。いずれも口座から引き落とされた日を発生日として計上しましょう。
有償のサポートサービスを利用した場合
クラウド型会計ソフトでは、不具合が発生したときに有償のサポートサービスを利用する場合があります。突発的な費用が発生した際の勘定科目については取り決めがありませんが、一般的には「支払手数料」や「諸会費」として計上します。
インストール型会計ソフトの勘定科目
インストール型会計ソフトとは、パソコンやサーバーにソフトウェアをインストールして使用するタイプです。インストール型会計ソフトの勘定科目は、購入金額によって4つに分類されます。
10万円未満の場合
購入金額が10万円未満の会計ソフトは、全額を「消耗品費」として計上します。消耗品費とは、事業で使う備品を購入した費用です。消耗品の購入費の他、使用可能期間が1年未満もしくは取得価額が10万円未満の什器備品の購入費も該当します。
10万円以上の場合
購入金額が10万円以上の会計ソフトは、「無形固定資産」(ソフトウェア)として計上します。会計ソフトをはじめとするソフトウェアの耐用年数は5年です。
減価償却には「定額法」と「定率法」2種類の計算方法がありますが、ソフトウェアには原則「定額法」が用いられます。定額法では、「取得価額×定額法の償却率」によって減価償却する金額を算出します。
10万円以上30万円未満かつ少額減価償却資産の特例を適用する場合
少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際に、費用を一時的に必要経費にできる制度です。少額減価償却資産の特例を適用する場合は、一度固定資産として計上し、決算で全額を減価償却費として計上しましょう。
10万円以上20万円未満かつ一括償却資産の損金算入の特例を適用する場合
一括償却資産とは、取得価額を3年間で均等償却できる一定の資産です。耐用年数にかかわらず、取得金額を3年間均等に費用として計上します。
経費管理におすすめの会計ソフト3選
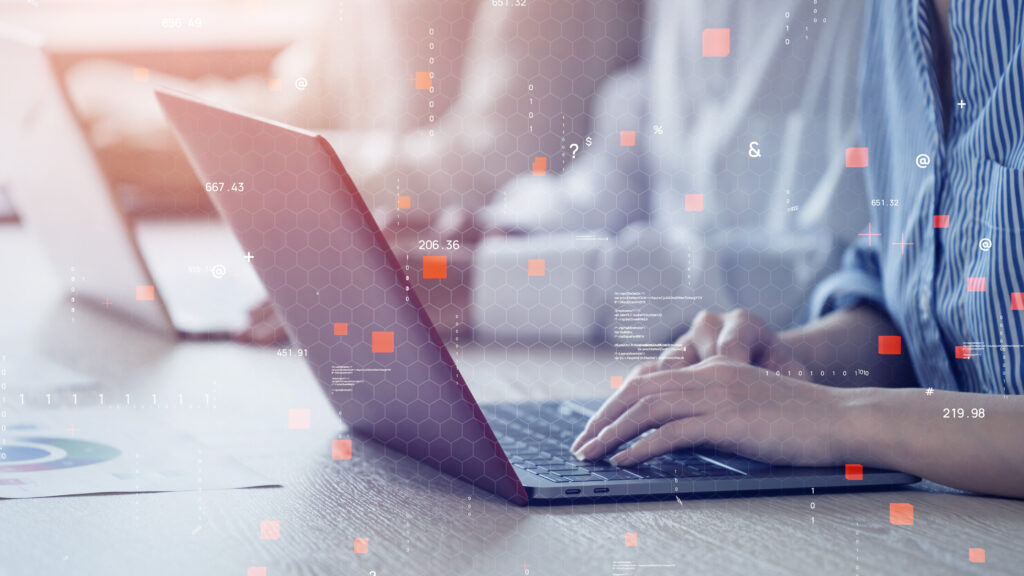
会計ソフトにはさまざまな種類がありますが、特に人気のある3つのソフトウェアを紹介します。
WEBバランスマン
WEBバランスマンは、公益法人向けの会計システムです。簿記の知識がなくても入力できる簡単設計で、多くの企業から支持されています。伺書入力機能が標準装備されており、作業の簡易化が図れます。変換マスタの利用で、「平成20年基準・平成16年基準」両方の決算書出力が可能な点も特徴です。予算書や決算書類の出力にも対応しています。世界のトップブランドであるジオトラスト社のSSL証明書を取得しているため、セキュリティ面も万全です。
freee会計
freee会計は、初心者でも簡単に利用できるクラウド型会計ソフトです。インボイス制度や電子帳簿保存法など、法令の変更にも自動でアップデート対応します。freee会計は1,000以上のサービスと連携可能で、簡単に帳簿付けができるため、帳簿に関する知識がなくても安心です。freee会計のもう1つの魅力は、各プランを30日間無料で利用できる点です。初期費用や解約料も一切かかりません。会計ソフトを手軽に導入したい方は、ぜひfreee会計を候補の1つに入れてみてはいかがでしょうか。
弥生会計
弥生会計は、連続25年売上実績 No.1を誇る定番会計ソフトです。使いやすさとサポート体制が充実しており、長年の信頼と実績があります。初心者でもすぐに使い始められ、帳簿付けから決算資料まで簡単に作成可能です。全国12,000以上の税理士・会計事務所とパートナーシップを結んでおり、無料で紹介するサービスも提供しています。弥生会計には、パッケージ版とクラウド版の両方が提供されています。パッケージ版は主に中小規模法人やWindowsをメインで使っている方に、クラウド版は主に小規模法人や起業したての方におすすめです。
会計ソフト購入時の勘定科目はケースバイケース
会計ソフトを購入した際の勘定科目に明確な決まりはありません。ただし、一般的なルールに従って計上することをおすすめします。クラウド型会計ソフトの購入費用は、「通信費」または「支払手数料」として計上するのが一般的です。インストール型会計ソフトの勘定科目は、購入金額によって4つに分類されます。適切な勘定科目を選択し、正確な会計処理を行いましょう。

 製品情報
製品情報 セミナー情報
セミナー情報 販売パートナー情報
販売パートナー情報 会社情報
会社情報 サポート
サポート




